2月7日は初午(はつうま)、2月の最初の午の日ことです。旧暦の初午の頃は、春本番を間近に控えて、農作業が始まる時期で、豊作を願い村社にお参りして、郷土料理の「しもつかれ」をつくり豊作を願ったと言われています。
しもつかれ
「しもつかれ」は圧倒的に呼び名はしもつかれですが、他の地区では、「しみつかれ」など呼び方は様々です。
栃木県はかつては、下野の国でした、名前の由来は下野から来ているようです。
また、別説でルーツは、平安時代の近江国の食べ物で「酢ムツガリ」に起源があるそうです。
大豆に酢、塩などをかけた食べ物を天台宗により北関東にもたらされたと言われます。
栃木県の郷土料理と申しましたが、県北や両毛地区(足利市ほか)は食さないようです。(当地は栃木県南東部)
かつては、食材の少ないこの時期に、工夫を凝らし有る材料を生かして、しもつかれを頂いたと思われます。
最近はめっきり少なくなった「しもつかれ」は各家庭にそれぞれの味があり味の伝承が遙か昔から続いています。
しもつかれレシピ
今回の新巻鮭の頭は、やや小さめでしたので、大根と人参の量を少なくしました。大きい新巻鮭の頭でしたら、大根2本と人参2本が適量ですが、今回は大根1本と人参2本と油揚げ2袋にしました。
新巻鮭の頭と骨は、圧力鍋で煮込む
圧力鍋に新巻鮭の頭と骨を投入して、水を少量注いで、数十分煮込みます。

圧力鍋で新巻鮭の頭を煮る
鬼おろしで、おろす
その間に、大根と人参を鬼おろしで、ステンレスボールにおろします。通常のおろし金でおろすと、細かすぎて、煮ているうちに溶けて独特の食感がでません。
[wc_row]
[wc_column size=”one-half” position=”first”]

しもつかれ用の大根人参
[/wc_column]
[wc_column size=”one-half” position=”last”]

大根人参をすり下ろす
[/wc_column]
[/wc_row]
油揚げをカット
油揚げ2袋を2cm角程度にカットします。

油揚げを2cm角にカット
各食材を鍋で煮込む
新巻鮭の頭と骨を煮込んだものを一番下にして、油揚げ、大根と人参を鍋に投入して、一煮立ちしたら、弱火で1時間から1.5時間程度煮込みます。
その後、酒粕1袋300g入りの半分程度を、鍋に投入して、溶きながら混ぜ合わせます。弱火で30分程度煮込んで味が馴染めば完成です。
[wc_row]
[wc_column size=”one-half” position=”first”]

カットした油揚げを投入
[/wc_column]
[wc_column size=”one-half” position=”last”]

すり下ろした大根人参を投入
[/wc_column]
[/wc_row]
[wc_row]
[wc_column size=”one-half” position=”first”]

しもつかれ煮込み完了
[/wc_column]
[wc_column size=”one-half” position=”last”]

しもつかれ煮込み完了盛り付け
[/wc_column]
[/wc_row]
あとがき
家庭により拘りがあり、大豆を入れますが、我が家では大豆は入れません。
大豆の風味が強く出てしまい、何時もの素朴な味わいが薄れてしまうからです。
とは言うものの、毎回微妙に味が違います。新巻鮭の塩分や素材の味で大いに変わりますし、大根そのものの出来によりまた風味が変わってしまいます。
ましてや、よそ様や、店舗販売されたものなど、全く味わいが変わってしまい、同じ味のしもつかれを食べられません。
今回も、塩や醤油などの調味料は一切添加しませんでした。新巻鮭に付いた塩分は、とても良い味が出ます。
余計な添加物は不要です。
熱いまま食べて良し、冷めてから食べるのもまた違う風味が楽しめて尚良しと、無くなるまで充分楽しめます。
関連記事
栃木県の郷土料理、ご汁を紹介しました。



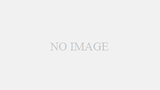
楽天広告